栽培こよみ 第32回
| オケラ キク科 |
| 長野を旅したときに、信州地方では「山でうまいはオケラにトトキ、嫁にやれない味の良 |
| さ」という歌があって、オケラとトトキは、おいしい山菜の代表なのだよと教えてもらっ |
| たことがあった。トトキとはツリガネニンジンのことである。この地方ではオケラもトト |
| キも山菜として食べていたというから、きっとそ |
| こらにたくさんあったのだろう。 |  |
| オケラもトトキも山野に自生していて、特徴の | |
| ある姿をしているから慣れれば簡単に見つけられ | |
| る。特にオケラの方は成長とともに葉が硬くなっ | |
| て、周りに針のようなトゲが一杯ついている。 | |
| 花が終わってからでもドライフラワーになって、 | |
| 咲いていた姿のままで残っているから見つけやす | |
| いのである。 |
 | オケラは園芸市場には流通しないようだから園芸店で見るこ |
| とはないが、茶花などとしての人気が高く、山野草を取り扱う店 | |
| などではよく販売されている。カタログにはオケラとオオバナオ | |
| ケラが掲載されていて、オオバナオケラは日本の植物ではないか | |
| ら薬用植物園でしか見ることはなかったが、今は山野草店で売ら | |
| れている。 | |
| オケラは丈夫な植物だから、庭に植えても、鉢に植えても比較 | |
| 的簡単に栽培できる。植える時期は春と秋がよく、したがって根 | |
| 茎もこの時期が手に入れやすい。 | |
| 自生地は日当たりのよい山地や田の土手などでみられるから、庭に植える時も日の当た |
| る水はけのよい場所に植える。地植えにするとほとんど手入れの必要がない。 |
| 鉢に植えるには5,6号の駄温鉢に赤玉土、日向土、鹿沼土を等量混合した培養土に腐 |
| 葉土を1割ほど加えて用いている。まず鉢底へ鉢底ネットを敷き、四分の一ほどに大粒の |
| 土を入れ、さらに培養土を鉢の半分程度まで入れてから根を広げて根茎を置く。その時、 |
| 新芽の出る位置ができるだけ鉢の真ん中に来るように置く。新芽は根茎の上に出ている数 |
| 個の白い部分である。 |
| そして残りの培養土を鉢の縁まで入れて軽く鉢底をとんとんと床に打ち付けると、表面が |
| 下がって1?程度のウオータースペースができる。 |  |
| たっぷりと水を与えて鉢植えの出来上がり。 | |
| そして少量の緩効性肥料を鉢の縁へ置いておく | |
| とよい。 | |
| 鉢はよく日の当たるところに置くのがよいが、真 | |
| 夏の強い光は避けるようにする。冬には地上部が枯 | |
| れるが寒さには強いので保護する必要はない。しか | |
| かし凍結するようであれば軒下などに取り込む。 |
| 春になれば白く柔らかい毛におおわれた新芽が伸びだす。この若芽を採り、茹でてお浸 |
| しや、和え物にする。また、汁の実、てんぷらに利用するのもよい。 |
| 根茎はお正月に飲む屠蘇散にも用いられる。古くには根茎の皮をむき、切って2、3日 |
| 水に晒してアクを抜き、煮て食べたようである。また、オケラを室内で燻蒸すれば湿気を |
| 取り、蚊よけになるともいう。そうして昔の人はオケラを上手に利用していたのである。 |
(2010年10月1日) |
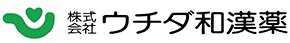
 漢方薬の剤形
漢方薬の剤形