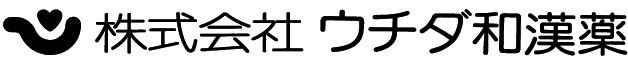日本薬局方(日局、第18改正)に「ニンジン(人参):GINSENG RADIX」と収載され、基原はオタネニンジンPanax ginseng C. A. Meyer (P. schinseng Nees)(ウコギ科:Araliaceae)の細根を除いた根又はこれを軽く湯通ししたものと記載されて、漢方では補気強壮薬として用いられる生薬です。本品は定量するとき、換算した生薬の乾燥物に対し、ギンセノシドRg1 0.10%以上及びギンセノシドRb1 0.20%以上を含むと規定され、性状は細長い円柱形~紡錘形を呈し、主根は径0.5~3cm、外面は淡黄褐色~淡灰褐色で、根頭部が除かれており、太くて重く充実して空洞が無く、特異なにおいを呈し、味は初め僅かに甘くて後にやや苦いものが良品とされます。
『神農本草経』の上品に収載され、根が人の形に似ていることから「人参」といわれ、古くから不老長寿、万病薬として珍重されてきました。中国東北部、朝鮮半島、シベリア沿海地方に自生する多年草ですが、朝鮮半島を中心に分布していることから「高麗人参」ともいわれます。和名は我が国では江戸幕府が栽培を奨励したことに由来します。御種人参(おたねにんじん)と呼ばれて各地の薬園などで栽培化が進められましたが、現在では福島県会津地方(会州人参)、長野県東信地方(信州人参)、島根県大根島(雲州人参)で生産されるのみとなっています。国産人参は高い品質と安全性が国内外で評価されてきましたが、産地では生産者の高齢化・後継者不足などにより生産規模が縮小し、耕作地の荒廃・放棄が急速に進んでいます。さらにコスト面で外国産に対抗できず、国内の需要は大半が中国、韓国産の栽培品によって賄われています。
市場品には修治や部位の違いにより、皮付きで乾燥した生干人参、皮付きで湯通しした御種人参、皮を剥いで乾燥した白参、皮付きを蒸して赤褐色になったものを乾燥した紅参、細根を乾燥したヒゲ人参などがあり、用途によって使い分けられています。漢方では主に御種人参が広く用いられています。なお日局には別条に「コウジン:紅参」が収載されていますが、本稿では人参について述べます。
成分としてはダマラン系トリテルペノイドサポニン(ギンセノシドRa~Rh類、主成分はRb1、Rg1)、アセチレン誘導体(パナキシノール)、多糖類などが含まれます。主成分のギンセノシド類に骨髄におけるタンパク質、DNA、RNA、脂質などの合成促進作用、抗疲労・抗ストレス作用、強壮作用、降圧作用、血糖降下作用、認知症改善効果など数多くの研究が報告されています。
性味は甘微苦・温、帰経は肺・脾で、大いに元気を補い、虚脱を治し、津液を生じ、精神安定をはかる効能があるので、労働過多による疲労、食欲不振、倦怠、未消化便の下痢、発汗性虚脱、けいれん発作、健忘症、めまい、頭痛、インポテンツ、異常子宮出血、慢性化した消耗性疾患、一切の気血津液の不足などに用いられます。
配合応用として、人参+黄耆・白朮は脾胃虚弱に伴う疲労感、病中病後の体力低下、糖尿病など体力が衰えて疲労しやすい慢性の虚弱体質を改善する「補中益気湯」、人参+黄耆・五味子は暑気あたりや病後で倦怠感が強く、食欲不振、軟便、自汗のみられるときの「人参養栄湯、清暑益気湯」、人参+黄耆・熟地黄は大病後や術後などで体力の衰えたときの「十全大補湯」、人参+蘇葉・葛根は虚弱体質者などの風邪の初期で倦怠感の強いときの「参蘇飲」、人参+白朮は胃腸の機能衰弱による食欲不振、倦怠無力、消化不良、腹部膨満感、慢性下痢、めまい、貧血、自汗を治す「人参湯、参苓白朮散」、人参+酸棗仁は消耗性疾患による心悸亢進、不眠、精神不安を治す「帰脾湯」、人参+石膏・粳米は糖尿病や熱病のためによる激しい口渇を治す「白虎加人参湯」、人参+麦門冬・半夏は慢性気管支炎などで咽喉の乾燥感があり咳嗽が強くて痰の少ないときの「麦門冬湯」、人参+附子は寒邪による胃腸機能の低下・腹痛・下痢を治す「附子湯、附子理中湯」などと、補気・健脾・安神・止渇作用を目標にした多くの漢方処方があります。
なお、人参には基原植物を異にする類似生薬があります。竹節人参は我が国に自生するトチバニンジン(P. japonicus)が基原で、江戸時代より人参の代用品として用いられています。人参に比べて滋養強壮作用は劣りますが、鎮咳去痰・健胃・解熱作用に優れるので、咳嗽や心下部の痞えを目標に用いられます。三七人参(三七・田七・田三七)は中国南部雲南省のサンシチニンジン(P. notoginseng)が基原で、『本草綱目』に初めて記載されました。漢方では、出血性疾患の止血・駆瘀血・止痛に広く用いられ、特に止血作用は大変強力です。リウマチ・神経痛の鎮痛薬としても用いられます。西洋人参(西洋参・広東人参)は北米原産のアメリカニンジン(P. quinquefolium)が基原で、人参に比べて疲労回復作用は劣りますが、滋陰・清熱作用に優れるので、熱証患者の滋養強壮に適しています。