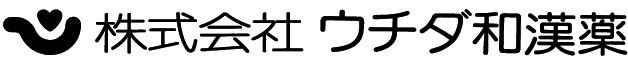平成29年(2017年)の干支は「丁酉」です。酉には動物としてニワトリがあてられています。ニワトリは、人間と関わりが深い鳥類で、紀元前に家禽としての飼育が始まり、世界各地に伝わったとされています。原種は東南アジアに生息するヤケイの仲間とされ、今では、卵用、食肉用の他、観賞用など多くの品種が生みだされています。
ニワトリに関する生薬には、鶏卵に由来する「鶏子」があります。『傷寒論』出典の黄連阿膠湯には、鶏卵の黄身である「鶏子黄」が配合されています。この湯液を作るには、卵黄は最後に加えますが、固まるのを防ぐために、煎じ液を少し冷ましてから入れることが大切とされます。また、『傷寒論』出典の半夏苦酒湯は卵の殻を利用して作ります。鶏卵から黄身を去り、白身を残して、そこに半夏と酢を加え、卵の殻ごと安置して倒れないように加熱すると記されています。
一方、ニワトリだけでなく鳥全般に目を向け、薬用植物について見てみます。和名に鳥が付くものには「トリカブト」があります。この名は、花の形が、日本の舞楽の時に使う「鳥兜」という頭にかぶる装飾品に似ているからだと言われています。トリカブト類の根は附子、烏頭として用いられます。また他に、メギ科の植物「メギ」には、「コトリトマラズ」という別名があります。枝が多く、トゲがあり、小鳥がとまれないことから名づけられました。メギは、ベルベリンを含み、胃炎や下痢に用いられます。
ところで、季節を表す七十二候に、「鶏始乳(とりはじめてとやにつく)」があり、1月末から2月初めの頃をさしています。ニワトリは本来冬には産卵しません。ニワトリが春の気配を感じて、卵を産み始めるのがこの頃とされています。この時期を過ぎると暦の上では春となります。暖かさを実感できる日はだんだんと近づいて来ているようです。