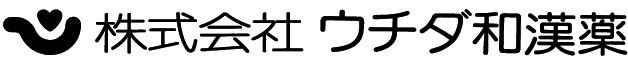|
アイ タデ科 中国から伝えられて鎌倉時代には栽培されていたらしいが、染料に用いたのは徳川時代からという。繁殖は実生によるが、園芸店から1鉢買ってきた株から種が飛んだのであろう。毎年、あちこちから芽を出すようになった。 | |

|

|
| 前画面へ戻る | |
|
クマヤナギ クロウメモドキ科 長さが30cmほどの苗を庭へ植えたところ、隣の木に枝を伸ばしてたちまちその木を覆うほどに繁茂した。丈夫なツル性植物で、ツルは鞭や樏の材料にしたらしい。薬用には茎葉を健胃、整腸、口内炎などに用いる。 | |

|

|
| 前画面へ戻る | |
|
シロツメクサ マメ科 英名のクローバの名で知られているが、ヨーロッパ原産の多年草である。牧草や緑肥として栽培されていたものが野生化したらしい。郊外に出れば路傍でも見かけることがある。薬用部分は全草。 | |

|

|
| 前画面へ戻る | |
|
ハアザミ キツネノマゴ科 最近、園芸店に苗が売られて、種苗会社のカタログにも掲載されているからよく知られるようになった。しかし、ラベルには学名のアカンサスの表示が多い。庭へ植えたところ、2mほどの長い花茎を伸ばして毎年、咲いてくれる。 | |

|

|
| 前画面へ戻る | |
|
ヤブコウジ ヤブコウジ科 ヤブコウジの赤い実の付いた株は、お正月の飾りに使うので知られていると思うが、花を見る機会はそうないだろうが、林床などに生える小低木。夏ごろ、葉えきに数輪の白色の花を下垂する。薬用部分は根。 | |

|

|
| 前画面へ戻る | |