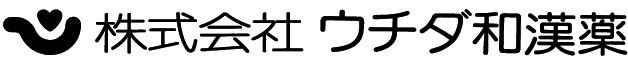基源:シャクヤク Paeonia lactifiora Pallas 又はその他近縁植物(ボタン科 Paeoniaceae)の根
ボタンは"木"、シャクヤクは"草"ですが、ともによく似た大きな
花を咲かせるので常に並び称されています。
ボタンとシャクヤクは生薬としても話題の多い植物で、両種でボ
タン科を形成する同じ仲間でありながら、薬用部位や薬効が違っ
ていて、いつも比較されます。今回はこれから花の咲くシャク
ヤクを話題にしたいと思います。
シャクヤクは、中国東北部、東シベリア、朝鮮半島原産の植物で、
花期は5月、中国ではずいぶんと早い時期から鑑賞用に栽培され
ており、わが国でも足利時代にすでに栽培されていた記録があり、
渡来時期はボタンよりも早いとされています。
シャクヤクは植物としてははっきりとしているため、生薬「芍薬」
の基源に関してもさほど問題がないように思われがちですが、実
際は品質面で種々異なったところがあります。すなわち、産地
(あるいは品種)によって成分的に大きく異なることはすでに指
摘されているところですが、それ以前の問題として、古来生薬
「芍薬」には赤芍と白芍の違いがあり、その定義が時代によって
変化してきているのです。
赤芍と白芍の薬効の違いについては『傷寒論』に「白いものは補
い、赤いものは瀉ぎだし、白いものは収め、赤いものは散らす」
と記され、また『蜀本草』では「赤は小便を利し気を下し白は痛
みを止め血を散ずる」とし、『日華子諸家本草』では「赤色のも
のは多く気を補い白は血を治す」と、書物によって違って述べら
れています。
一方、薬物学的には、芍薬は『新農本草経』の中品収載品で、そ
こには赤白の区別はありませんが、梁の陶弘景は赤芍と白芍の区
別があることを記しています。
宋代になると、『図経本草』には「准南のものが勝る。(花色は)
紅白紫数種ある。根もまた赤白二種ある」と記され、さらに崔豹
古の意見として「芍薬に草芍薬、木芍薬二種あり。木芍薬は花が
大きくて色が深い」、また安期生の服錬法を引用して「芍薬に二
種あり。一つは金芍薬、二つは木芍薬。病を救うのに用いるのは
金芍薬で、色が白く太っている。木芍薬は色は紫で痩せて脈が多
い」と記しています。崔豹古の草芍薬と安期生の金芍薬、また木
芍薬が同じ基源なのかどうかはわかりませんが、このころ薬用と
していたのは金芍薬すなわち白芍だったこと、また赤芍・白芍は
根の色、大きさ、形などで分けられていたことなどが窺い知れま
す。また、『証類本草』には「別説云」として「薬用には家に植
えられているものが多く用いられている」ことや「昨今は多くは
栽培品を薬用にしているが、(肥料を多く施した結果)根が肥大
して香味がないものは薬用には適さない。やはり川谷丘陵地に生
えているものが勝る」とする意見を引用しています。すなわち、
当時は白芍としては栽培シャクヤクを、赤芍として野生品を利用
していたようです。
明代になると、李時珍は『本草綱目』の中で「日華子のいう、赤
が気を補し白は血を治す、というのは審に欠ける」、また「白は
金芍薬、赤は木芍薬。根の赤白は、花の色に従う」と述べていま
す。すなわち、白花の品種(または花色の薄い品種)の根を白芍
とし、赤花(または花色の濃い品種)の根を赤芍としたわけです。
そして現在中国では再び、白芍を栽培品種の根、赤芍を野生種ま
たは P.vcitchii Lynch の根(川芍薬あるいは川赤芍)として
いますが、野生品を白芍として使用する地方もあるようです。
芍薬の品質は一般に、太くて内部が充実し、やや柔軟性を帯び、
内部が微赤色から白色を呈し、収斂性とやや苦みがあり、芍薬特
有の臭いが強いものが良いとされ、内部が暗色を呈するものは劣
るとされています。また、産地によって「抗芍」,「毫芍」,「川芍」
,「中江芍」などがありますが、品質は「抗芍」(浙江省産)が最
良だと言われています。『図経本草』には「准南」(すなわち今の
安徽省)のものが勝れているという記載がありますが、これは今
の「毫白芍」に相当し、産出量の最も多いものです。
一方、李時珍は揚州芍薬が優れていると述べ、良質芍薬の生産地
も時代によって移り変わりが見られます。また、他書に花の色や
花弁の状態で芍薬の品質の良否を論じたものがありますが、これ
も一定していません。
芍薬はわが国で自給率の高い生薬の一つですが、現在は赤白を区別
せず、コルク層を削り温風乾燥または風乾したもの、あるいは皮を
剥いだ後に煮沸または蒸すかして調製したものを単に日局シャクヤ
クとして用いています。ただし古くは根を水洗しそのまま曝乾した
ものを赤芍、水洗後外皮を剥いで煮沸するか蒸した後に曝乾したも
のを白芍としていました。
これはおそらくわが国には薬用に適した野生品がなかったからでし
ょう。過去現在を問わず、まさに日本式にアレンジされた利用法で
すが、中国でもともと区別のなかったものが区別されるようになっ
たのにはそれなりの理由があると考えると、以上ご紹介した内容を
もとに一考してみる姿勢も必要かも知れません。
生薬の玉手箱 | 芍薬(シャクヤク)
芍薬(シャクヤク)
生薬の玉手箱 No.020
(神農子 記)