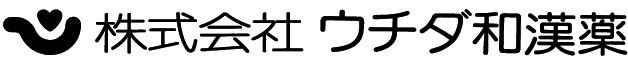基源:シソ Perilla frutescens Britton var. acuta Kudo 又はその他近縁植物(Labiatae シソ科)の葉および枝先である。
シソの葉は梅干作りに欠かせない材料で、われわれ日本人にとって日常生活でたいへん馴染みの深い植物です。また、青シソの葉が刺身に添えられるのはその殺菌作用をうまく利用したものであることも良く知られており、解毒作用が有るとも言われます。今でこそ単なる飾りになってしまっていますが、昔は魚介類による中毒が多かったものと思われ、シソの葉は欠かせないものであったに違いありません。
薬用としてのシソは『名医別録』に「蘇」の名前で初めて収録されました。同書には「とりわけ其の子が良い」と種子の効果が優れていることが記されています。その後、陶弘景は「葉の下面が紫色で気が甚だ香るものだ。紫色でなく香気もなくて荏(エゴマ)に似るものは野蘇で、使用に耐えない。その種子は主に気を下す働きがあり、橘皮と同じ治療効果がある」とし、やはり薬用には種子を用い、葉についてはまったく触れられていません。葉の効能が明記されるのは宋代の『図経本草』です。「蘇とは紫蘇のことで(中略)夏に茎葉を採り秋に実を採る。茎と葉は心経を通じ脾胃を益する。煮て飲用するのがもっとも優れ、橘皮とともに気剤の中には相宜しく之(茎葉)が多く用いられる。実は(種子)上気咳逆をつかさどり、研じた汁を煮て用いるのがもっとも佳」とあり、茎葉と種子では薬効が異なることも記されています。これはすなわち「蘇」を神経症に用いるには茎葉が、逆上(のぼ)せに用いるには種子が優れていると解釈できます。
さて、現在わが国では薬用にはもっぱら葉を利用し、種子(蘇子)はあくまで代用品として取り扱われています。しかし、蘇子の方が薬効が安定しているので使いやすいとする意見も有ります。それほど葉の気は抜けやすいものです。
葉類生薬は一般に新鮮なものが良いとされます。乾燥して保存するうちにシソ特有の香りが徐々に薄くなることからしても、薬効も徐々に劣ってくるものと考えられます。そうなれば保存期間の長さ(新旧の程度)によって使用する量を変化させねばならないのでしょうか。ただ、先にも書きましたように、葉と種子では本来薬効が異なるようです。実際、種子にはシソ特有の香りはほとんどありません。
また、シソの仲間には多くの品種があります。本草書にある「葉の下面が紫色」をしたものはカタメンジソと呼ばれる品種で、昨今は両面が紫色をしたシソや葉の縮れたチリメンジソが最良品であるとされています。なお精油の主成分であるペリラアルデヒドの臭いが強いものほど良品であるとされるのは昔から変わっていません。
いずれにせよ「蘇葉」は数少ない気剤の一種です。紫色が茶色く変わり香りの薄れたものに薬効は期待出来ないと考えられます。身近で安価な薬物であるからこそ、常に新しいものを準備して利用したいものです。とは言え、一年草のシソの葉が収穫できるのはほんの1シーズンに限られます。我々も収穫後の保存には十二分に気を使っています。