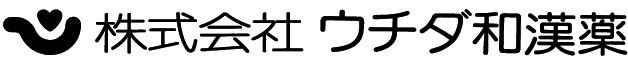基源:ケイガイ Schizonepeta tenuifolia Briquet(シソ科 Labiatae)の花穂。
「荊芥」の名は、『神農本草経』には見られませんが、「假蘇」の名で収載されているものと同一であるとされています。その根拠は、『名医別録』で假蘇の一名に「薑芥」があげられ、『新修本草』で荊芥(ケイガイ)は薑芥(キョウガイ)の音が転訛したものであると記載されていることです。また、荊芥の名が項目として初出するのは『呉普本草』で、李時珍は「『呉普本草』(呉氏本草)の編者である呉氏は、東漢末の人であり、『名医別録』編纂時期に近く、唐代の蘇恭(新修本草)はそれを祖述した」、と記して『新修本草』の記載の信憑性を強調するとと同時に、「陳士良と蘇頌が假蘇と荊芥を違うものとしているのは、あくまで臆説であると思われる」と假蘇と荊芥の不同一物説を否定しています。ただし、假蘇の假は"仮の"という意味であるところから、假蘇は蘇の代用品であったと推測でき、陳士良と蘇頌の説もあながち否定できず、その基源は荊芥のみではなかったものと考えられ、さらに荊芥の原植物も混乱していたことが予測されます。
そこで、中国の各地方で現在「荊芥」と称されている植物を調べてみますと、Schizonepeta属、Salvia属、Nepeta属、Origanum属、Ocimum属など、シソ科の複数の属にわたっていることがわかりました。いずれも全草に芳香を有する種類で、シソの香りに似ている点で「假蘇」の素質を具えた植物と言えます。その他「土荊芥」としてシソ科以外にゴマノハグサ科、クマツヅラ科植物由来のものがあることもわかりました。このように、古来荊芥の原植物は大きく混乱していたものと思われますが、花が密生した穂を作り、『呉普本草』中の「葉が細い」という記載によく符合するのは現在の原植物 Schizonepeta tenuifolia であり、『図経本草』の成州假蘇の図も本種によく似ています。
荊芥は『証類本草』の中では「菜部中品」に収載されています。陶弘景は「方薬には用いない」とし、『新修本草』には「人はこれを食するという記録がある」とあり、地上部は本来野菜であったと考えられます。薬用としては『図経本草』に「穂をなしたものの花実を採って暴乾し、薬に入れる」、『本草衍義』にも「穂を用いる」の記載が見られるところから、古来薬用には花穂のみが利用されてきたものと判断できます。
一方、日本と中国の薬局方を見ますと、ともに原植物は同じですが、薬用部位は日本では花穂のみで、中国では地上部を単に「荊芥」とし、花穂を「荊芥穂」として区別しています。荊芥穂は芳香気烈で効能が荊芥よりも強いとされており、地上部は別に野菜としても利用されてきたことから、習慣的に両者が使い分けられてきたのだと思われます。
荊芥はたいへん良い香りのする生薬です。薬効的には紫蘇や生姜と同じく辛温解表薬に分類され、表を解し風を散ずる薬物として、透疹、感冒、頭痛、麻疹、風疹、腫物の初期などに用いられます。「荊芥連翹湯」や「清上防風湯」に配合されています。