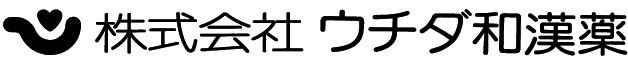基源:トウガラシCapsicum annuum L.又はその変種(ナス科Solanaceae)の果実。
トウガラシは,熱帯アメリカすなわち新大陸原産の植物です。種小名のannuumは「1年性の」という意味ですが,原産地では多年性の低木となります。ただし,わが国のような温帯で育てると周知のように一年草の性質を示します。
昨今はトウガラシは世界中で利用される重要な香辛料となっていますが,原産地の新大陸から持ち出して世界中に広めるきっかけを作ったのは,ほかでもないコロンブスであったことは良く知られています。西インド諸島への第二次航海の時で,1494年のことです。こうして先ずはヨーロッパ(スペイン)にもたらされたトウガラシは,当時高価であった肉料理に欠かせない香辛料コショウに取って代わり,急速に広まりました。それから極東アジアのわが国に伝わるのに100年しか要さなかったことは驚異的とも言えます。わが国への伝来についてはいくつかの説があり,種々の記録からは秀吉の朝鮮出兵の際に種子がもたらされたとするのがもっとも信頼性が高いようですが,決定的ではないようです。
さて,薬用としてのトウガラシは,原産地においては約7000年前から利用されていたことが知られており,健胃薬としてのほか,痙攣や下痢の治療に内服され,歯痛にはこれを歯肉に塗布したそうです。現在の『日本薬局方』では本質は局所刺激薬とされていますが,辛味性健胃薬としても知られています。一方,原産地で歯痛に塗布薬として利用されていたように,皮膚に塗布すると知覚麻痺を起こすことが古くから知られていました。その活性成分は辛味成分のカプサイシンで,最近では感覚ニューロン遮断薬としての作用機序も解明されています。
ヨーロッパにおいても導入後まもなく,薬用としての利用も始まったようです。実はトウガラシが『日本薬局方』に初収載されたのは第三版(1906年)です。人参や黄柏の収載が第六版(1949年)であったことを思うと随分と早く,ヨーロッパの影響すなわちトウガラシチンキが多用されたことがうかがえます。今も本質が局所刺激薬となっている所以です。
さて,中国では如何であったかというと,食用としてはすぐに広まりましたが,薬用としてはそれほど重要視されなかったようです。中国では明代後半には全土に広がっていたと考えられていますが,本草書に記されるのは清代になってからで,『本草綱目拾遺』に「辣茄」の名で,「人家の園圃に栽培され,深秋になると山の人たちが市場へ売りに来る。空煎りして柔らくなった果肉の絞り汁で凍傷を洗う」と民間的に「しもやけ」に用いられたことが記されており,わが国での利用法と共通している点は「唐辛子」の語源とあいまって興味があります。近年は「辣椒」と称されていますが,未だに薬用植物としての確たる地位を得ておらず,『中華人民共和国葯典』や『中葯志』にも収載されていません。
一方,わが国では,江戸時代(1671年)の『庖厨備用倭名本草』調★(★:食へんに壬)類に「番椒」の名で,「味辛ク性温。毒ナシ。宿食ヲ消シ,結気ヲ解キ,胃口ヲヒラキ,邪悪ヲ辟ケ,腥気諸毒ヲ殺ス」と効能が記されており,その後の『大和本草』では,菜類の項に「蕃椒をよく乾燥して粉末とし,糊とまぜて紙や布に広げ,身体の痛みのある場所に貼ると甚だ効果がある.また感冒には脊椎の第3と第4番目の間に貼り,衣を厚めに着込んで発汗するのがよい」などと記されています。こうした薬効はヨーロッパからの知恵であったようにも思われ,そうするとトウガラシはポルトガルからもたらされたとする説がもっともらしく感じられ,また別名の「南蛮」も意味をもってきます。ただ,蕃椒に「こうらいごしょう」のルビがある点は朝鮮半島を思いおこさせます。トウガラシの性味が「辛・温」だとすると,解表薬として利用できるはずです。食用すると汗が噴き出るのはまさに辛温解表薬の特徴です。なぜ中国で利用されなかったのかが不思議でなりません。他にすぐれた辛温解表薬があったからなのでしょうか,あるいは新参者であったからなのでしょうか。新大陸を出てたかだか500年の歴史しかないのに,調べてみるとあまりにも分からないことが多すぎます。日本への渡来説の真偽をも含めて,一考を要することがまだたくさんあるようです。