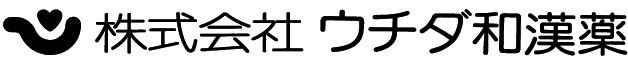基源:キクChrysanthemum morifolium Ramatuelle (キク科Compositae)の頭状花。
キクはサクラと共に日本を代表する花とされていますが、いわゆる観賞用のキクはもとは中国から薬用植物として8世紀あるいはそれ以前に導入され、栽培されるようになったとされます。中国からの他の多くの導入植物と同様、おそらく薬用としてもたらされたものと思われ、わが国最初の漢詩集『懐風藻』境部王の作に出てくる<菊酒>、『古今和歌集』中の<菊の露>、『紫式部日記』中の<菊の着せ綿>など、すべてキクの僻邪除災や不老長寿の効能にかかわる行事などに関する詩や記事であったことからもうかがわれます。
薬用としてのキクは『神農本草経』の上品に「菊花」が収載され、「味は苦平。風による頭眩や腫痛、目が脱けるように涙出するもの、死肌、悪風、湿痺を治し、久服すれば血気を利し、身を軽くし、老に耐え、年を延す。一名節華」と記載されています。
栽培種のキクは、ハイシマカンギクとチョウセンアブラギクの雑種から品種改良されて今のように多種多様になったとされていますが、ノジギクやリュウノウギクから改良されたとする説もあります。いずれにせよ、中国ではずいぶんと古い時代から植物の交配による品種改良が行われていたことになります。ただ、中国におけるキクの改良は唐代であるとされ、『神農本草経』の時代はまだ野生種が利用されていたことになります。
キク科植物にはいわゆるキクの仲間Chrysanthemum以外にも花の形が良く似た植物が多くあります。一方、陶弘景が「茎が紫で気が香り、味が甘く、葉は羹に作って食べる。これが真の菊である。茎が青く大きくなりヨモギのように気味は苦く、食べることのできないものは真ではなく、苦?である」と述べ、よい香気があって葉を食用にするもの、すなわち今の食用菊と同じChrysanthemumがやはり正品であったことは間違いなさそうです。
一方、Chrysanthemumといえども野生品には種類が多く、品種改良されたキクをも含めると花の色もさまざまです。また地方的にも分布する種類は異なっています。当然異物同名品が多く存在したことが予測されます。花の色は目立つ形質だと思われますが、中国の本草書に現れるのは宋代の『本草衍義』が最初で、「菊は20種あり、中でも花は一重で小さく黄色で、葉は緑が深く小さく薄く、9月に花の開くものが正品である」とあります。しかし、現在中国の『中薬大辞典』には「香りがすがすがしく、味は薄くてわずかに苦く、色が鮮やかなものが佳品である」とされ、亳菊(白菊ともいわれる)や?菊が良品であるとされており、これらの舌状花は白色です。古代から現代に到るまでに花の色が変化してしまったわけですが、明代の李時珍は「茎・花・葉の形や色はそれぞれ異なり、味にも甘、苦、辛の差異がある。食用にするには甘いもので、薬用には甘くても苦くてもいづれでもよい。ただ、野菊(苦?)だけは用いない。黄花のものは金・水(肺・腎)の陰分に入り、白花のものは金・水の陽分に入り、紅花のものは婦人の血分に入り、いずれも薬用にする」と、花の色の違いによる薬効的な使い分けを述べています。そして、現代中医学では、黄菊花で味の苦いものは泄熱にすぐれているとして疏散風熱に用い、白菊花で味の甘いものは清熱にすぐれているとして平肝明目に利用しています。
以上のことを考え合わせると、菊花は花の色よりもChrysanthemumに独特な香りの方が大切なような気がします。そう言えば、中国には中に生薬が入った薬用枕というものがあって、安眠枕には菊花が入っています。まさに香りの効能を利用したものといえます。
一方、「菊花」の偽品とされる「野菊」についてですが、一般に「野菊」の用語が「野に咲くキク」の総称である限り、人によって思い浮かべる姿はさまざまであるに違いありません。野に見るキクの花の多くは、例えばマーガレットのように、花びら(実は一つ一つが花で、舌状花と言う)が周囲に1列に丸く並んだ花(頭状花)で、ダリアやタンポポのように中までぎっしりと花が詰まった品評会などで見るキクは、どちらかと言えばまれです。そして、俗にノギクと呼ばれている多くのキクは、実際には花が薄紫のヨメナやノコンギクであることが多く、真のキクの仲間Chrysanthemumではないようです。わが国に野生するChrysanthemumの花の色は純白か黄色です。また、キク特有の芳香もChrysanthemumの花に強く、他にも同じような花の形をしたキク科植物が数多くありますが、それらにはあっても弱いようです。やはりこれが薬効成分なのでしょうか。