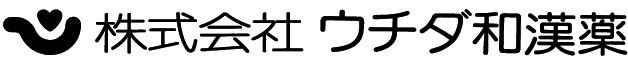基源:ビワEriobotrya japonica Lindle(バラ科Rosaceae)の葉。
ビワはヒマラヤ山脈の暖温帯から亜熱帯にかけて自生する常緑高木で,約25種が知られ,多くは中国中南部からインドシナ半島北部に見られます。漢名の「枇杷」は葉の形が楽器の琵琶に似ていることから付けられたものとされますが,果実の形もまた琵琶に似ています。属名のEriobotryaはギリシャ語のerion(羊毛)とbotrys(ブドウの房)に由来し,ブドウの房のようになる果実に柔らかな毛が密生することに由来したものと思われます。わが国にも大分県,山口県,福井県などに野生と思われる木がありますが,平安時代の『本草和名』に「比波」の名で記載があり,奈良時代に薬用としてもたらされたものが全国に広がったものと考えられます。
中国におけるビワの薬用の歴史は古く,『名医別録』中品に枇杷葉の名称で,「味苦平無毒。急に起こった激しい乾嘔が止まないものを治し,気を下す。」と収載されています。陶弘景は「煮る暇がないときは,ただ噛んで汁を飲むだけでも癒える。」と述べ,李時珍は具体的効能について,「胃を和し,気を下し,熱を清し,諸毒を解し,脚気を療ず。」と記しています。また古来中国では,反胃による吐き気や水の飲みすぎによって起こった温病による吐き気に,毛を去って香ばしく炙った枇杷葉を他薬とともに煎服し,鼻血が止まらないときには毛を去って香ばしく焙じて末にしたものを茶剤として服用し,また痔瘡腫痛には烏梅湯で洗浄した後に蜜炙した枇杷葉を貼り,痘瘡潰爛には煎湯で洗うなどと,枇杷葉を多様に利用してきました。ビワの葉が配合される処方には,「枇杷清肺飲」,「枇杷葉飲」などがありますが,いずれにせよ葉の背面にある絨毛が湯剤に入ると咽に刺激があるため,一般には布で包んで煎じられます。
わが国では,江戸時代の『和漢三才図会』に,『本草綱目』の内容を節録して,「葉,苦平。肺胃の病を治す。すべてその下気の功を取る。熱を清し,暑毒を解す。また吐き気の止まらないものを治す。使う時には火で炙って布で毛を拭い去る。さもなくば肺を射て咳を生じる。和方に枇杷葉湯がある。食傷および霍乱を治すのに優れている。」と記載がみられ,中国と同様の効果を期待して,同様の方法が行なわれていたことが伺えます。また,江戸時代の京都,東京,大阪では,"びわ葉湯売り"が都大路を売り歩いたといわれ,さらに東海道の宿場では旅人の咽喉の渇きを癒し,また霍乱(暑気あたりによる吐き下し)の予防にふるまわれていたといいます。皮膚炎やあせもに煎湯で洗うことをも含め,民間薬としてもかなり広く利用されていたようです。
品質については,『図経本草』には「四月に葉を採って爆乾して用いる。」,『雷公炮炙論』には,「用いるには,採集して量ったときに,生の場合は一葉一両,乾燥したものでは三葉で一両の重さのものが気が充足していて用いることができる。」と記され,一色直太郎氏は「若い木から採った,極めて大なる葉を陰干しになしたもので,なるだけ青みを帯びた新しいものほどよろしい。」とし,果実が成熟する前のみずみずしくて勢い旺盛な,とくに大型の葉が良品とされていました。
ところで,ビワの花が晩秋から冬にかけて咲くと言うことはあまり知られていないのではないでしょうか。大きな円錐花序に白い花がたくさんつきますが,それほど目立った花ではなく,すでに野山や植物園へ出かけたりするシーズンが過ぎてしまっていることも手伝って,見る機会が少ないものと思われます。いずれにしても,この花からは初夏に出てくるビワの実は想像できません。