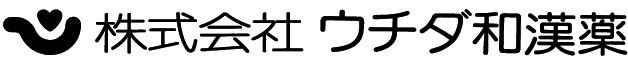基源:ツルドクダミPolygonum multiflorum Thunb.(タデ科 Polygonaceae)の塊根。
何首烏は『開宝本草』に初収載され,「心痛を止め,血気を益し,髭髪を黒くし,顔色を悦ばせる」効果があると記されています。漢方では稀用生薬ですが,滋陰養血,キョ風止痒薬として当帰,芍薬,川キュウなどと共に『済生方』収載の「当帰飲子」に配合されています。現在市場に流通するものはサツマイモを小型にしたような色形で,堅くて重質感のあるものです。
何首烏の原植物は現在の『日本薬局方』や『中華人民共和国葯典』にタデ科のPolygonum multiflorum Thunb. ツルドクダミであると規定されています。ツルドクダミは中国原産の蔓性植物で,蔓は細く,他物に絡まり,覆うように繁茂します。葉は互生し,葉腋から出る円錐花序に細かい白い花がたくさん咲いて目立ちます。一方,『開宝本草』には原植物の特徴として,「紫色の蔓で,黄白色の花を有し,葉は薯蕷のようで,必ず相対する」と記載されており,花の色や葉のつき方が一致しません。また,『図経本草』の付図にある「西京何首烏」の葉は互生しているように見え,また3小葉からなっており,このものも明らかにツルドクダミとは異なります。何首烏には古来赤・白の別があったことからも,原植物に混乱があったものと考えられます。
何首烏の赤・白については,『開宝本草』に「赤白二種有り,赤者は雄,白者は雌」とあり,『図経本草』にはこの雌雄について「雌の者は苗が黄白で,雄の者は黄赤である」と蔓の色で区別し,さらに「夜は則ち苗蔓相交わる・・・雌雄を兼ねてこれを採る」と両種を共に採集するとし,李時珍も「何首烏は赤白各一斤を用いる・・・白者は気分に入り,赤者は血分に入る」としています。このように生薬を赤・白二種に分ちながら,実際の処方中には同量が配合されるというのは,他の生薬には見られない特徴だと思われますが,原植物を含めて実態は不明です。
わが国では『多識編』(1612年)に「何首烏」の最初の名称記載があり,この頃にもたらされたものと考えられます。宋代の処方を研究するうちにその導入が意図されたのでしょうか,徳川吉宗により1720年に長崎にもたらされたとされ,駒場薬園で栽培が行われました。このものはツルドクダミであったと考えられ,繁殖力が旺盛で,今では日本各地に野生化し,葉がドクダミに似て蔓性であることからツルドクダミの和名がつきました。また学名のPolygonumは多節(茎), multiflorum は多花であることに由来します。
何首烏の原植物の混乱は現在にも引き継がれ,現在の何首烏はツルドクダミ由来のいわゆる赤首烏とされるもので,白首烏(白何首烏)は中国では一般に大根牛皮消Cynanchum bungei Decne.の塊根,韓国ではコイケマCynanchum Wilfordi Hemsleyがあてられており,ともにガガイモ科 Asclepiadaceae植物の根を乾燥したものです。かつて赤・白の何首烏の異物同名品としてそれぞれどのようなものが用いられてきたかははっきりとしていませんが,少なくとも『図経本草』の記載からは白首烏と赤首烏は単に蔓の色が異なる同一植物に由来していたようにも思われます。
化学成分としては,赤首烏はクリソファノール,エモジンなどのオキシメチルアントラキノン誘導体の他,タンニン,デンプンなどの成分が報告されています。一方の白首烏はシナンコールなど強心配糖体反応のあるものを含むという報告があり,ツルドクダミ由来の赤首烏とは含有成分が異なっています。このように同一の名称を持つ生薬で,赤白に使い分けられている生薬にはいくつかあり,それぞれの相違点など興味の湧くところです。
なお,何首烏の語源については,『図経本草』に,これを服して130歳まで生きた何首烏という人名に由来するとする逸話が引用されています。