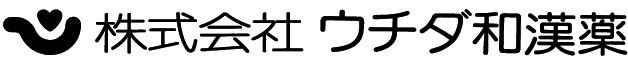基源:Cinnamomum cassia Blume (クスノキ科Lauraceae) の樹皮または周皮の一部を除いた樹皮.
『神農本草経』の上品には桂の字がつく生薬として「牡桂」と「箘桂」が収載されており,また『名医別録』では,そのほかに単に「桂」の記載が見られます.桂皮については,原植物,呼称,産地,薬用部位,香料か薬用かの違いなどの点からこれまでに種々の説があります。
李時珍は『本草綱目』の中で、「名医別録に収載される桂に牡桂と箘桂がある。牡桂は肉桂の皮の薄いもので、更に薄いものが桂枝である。桂とは肉桂であり、葉は長く枇杷葉のようで、堅硬で毛があり、鋸歯があり、花は白く、皮は脂が多い。箘桂は柿の葉のようで尖って細く、光浄で、三縦紋があり、鋸歯はなく、花は黄色あり、白色あり、皮は薄くて巻くものである。箘桂の種類に枇杷葉や梔子葉のような巌桂があり、俗に木犀と呼ばれる。花の色によって銀桂、金桂、丹桂などと称され、薬用にはされず、香料として用いられる。」としています。
以上のことから,「牡桂」と「箘桂」は種が異なる植物であることがわかり、李時珍はそれぞれの葉の特徴として牡桂の原植物を枇杷の葉にたとえ、箘桂の原植物を柿の葉にたとえています。ビワの葉は大型の長楕円形、あるいは倒皮針状で、鋭頭で基部は狭く、一方のカキの葉は楕円形であり、二者の様子はかなり異なります。『中国植物誌』所載のCinnamomum属植物の中からそれらをあてるとすれば、Cinnamomum節とCamphora節に属する植物になり、牡桂には葉の大きいC. cassia, C. verum, C. bejolghota (=C. obtusifolium) など複数のCinnamomum節植物が候補にあげられますが、樹皮を薬用に用いる白花種という厳密な条件からはC. cassiaに限定されます。ただし、本属植物の葉はすべて全縁で,李時珍が鋸歯があるとすることにはいずれの植物も一致しません。あるいはこれら植物の葉縁が波うつことを鋸歯と言ったのでしょうか。箘桂については、別の科に属するものをも含めさまざまな種類があったことがうかがえ,現時点では詳細は不明です.
李時珍は、更に、半巻きのものや板状のものを「牡桂」、巻くものを「箘桂」としており、牡桂は樹幹の皮で、箘桂は枝の皮を剥いでシナモンスティックのように巻いたものであったことがうかがえます。これらの違いは薬用と香辛料という用途の違いであったようにも考えられます.
Cinnamomum属植物の樹皮の利用は,古来西方と東方では利用目的が異なっており,東方では主に薬用に発汗・散寒薬とし,西方では主として香料・香辛料として用いられてきました。元来,桂皮など香りのよい植物は,神や霊を喜ばせたり,神との交流の場を作り出し,また良い香り成分を含む植物を身につけることにより清涼感が得られるとともに体臭を消すことから,古代エジプトや古代インドにおいて利用されてきました.東方の代表が沈香であるのに対し,西方ではシナモンとよばれるものが乳香や没薬と並んで代表とされてきました.ただし,古代のシナモンはCinnamomum属植物ではなく同じクスノキ科のRavensara aromaticaであるとする説もあります。後にインド産のC. tamala,インド南部のC. verumに代わり,アラビア商人が東南アジアを行きかうようになった結果,スマトラ産のC. burmanni,ベトナム産のC. bejolghota, C. cassiaなどがカッシアの名称で西方に運ばれるようになったそうです。現在、ヨーロッパではシナモンの名称で最も高貴な香りとされるセイロンニッケイC. verumが貴ばれ、その代用としてC. cassiaが知られています.
『中華人民共和国薬典2005年版』では,Cinnamomum cassiaの樹皮を「肉桂」,嫩枝を「桂枝」と別記載され,原植物は同一ですが,性味,帰経,効能等が若干異なり,部位が異なる別生薬として規定され使い分けられていますが,少なくとも李時珍の記載の中には嫩枝そのものを薬用にするという記載は見られません.いずれにせよ嫩枝に由来するものは日局には適合しません。