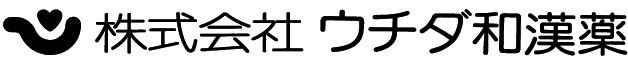基源:ヤマノイモ Dioscorea japonica Thunberg 又はナガイモ D. batatas Decaisne(ヤマノイモ科 Dioscoreaceae)の周皮を除いた根茎(担根体)
山薬の原植物であるヤマノイモとナガイモは共に,芋(担根体)が広く食用されており,日本では植物名と青果市場における芋としての通称とが混乱しています.ヤマノイモは日本の本州以南の山野に自生する植物で,その芋は「山芋(やまいも)」,「自然薯(じねんじょ)」,「自然生(じねんじょう)」などと呼ばれます.一方,ナガイモは中国から日本にもたらされた植物で,日本には自生しておらず畑で栽培されています.ナガイモにはいくつかの品種があり,細長い芋をつけるナガイモ群,掌状の芋をつけるイチョウイモ群,球状の芋をつけるツクネイモ群に大別され,それらの芋は「山芋(やまいも)」,「長芋(ながいも)」,「銀杏芋(いちょういも)」「大和芋(やまといも)」等の名称で流通しています.また,「山芋(やまいも)」あるいは「山の芋(やまのいも)」という言葉は,日本において食用とされるDioscorea属(ヤマノイモ属)植物の総称としても使われています.
ヤマノイモはつる性の植物で,他の植物などを支えによじ登りながら生長します.葉は対生で,長い柄があり,葉身は長卵形で先は尖り,基部は心臟形になります.雌雄異株で,夏に葉腋から花序を出し,雄花序は直立し,雌花序は垂れ下がります.果実は?果(さくか)で,晩秋に薄い翼をもった扁平な種子が飛散します.また秋から冬にかけて直径1〜2センチのむかごが葉腋につきます.ナガイモの植物体の形はヤマノイモとよく似ていますが,ナガイモではつる性の茎と葉柄がともに紫色をおびることで区別することができます.薬用部位である芋は植物学的には担根体と呼ばれ,地上茎基部の節間が側方に肥大成長した,枝も葉もできない特殊な茎で,貯蔵器官としての役割もあります.ヤマノイモの芋は,地下の障害物を避けながら約1メートルも伸び,地面に近い所では細く,深い所ほど太くなります.秋から冬にかけて地上の枯れたつるを目印に掘り取りますが,長い芋を掘るのは大変な作業です.
山薬は,『神農本草経』の上品に「薯蕷」の名で「傷中をつかさどる.虚羸を補し,寒熱邪気を除き,中を補し,気力を益し,肌肉を長じる.久しく服すれば,耳,目を聡明にし,身を軽くし,飢えず,長生きする.」と記載され,牛車腎気丸,八味地黄丸,六味丸などの処方に配合されています.現在では生薬には「山薬」という名称が用いられますが,この理由について寇宗奭は「薯蕷は,唐の代宗の名が預であったところから諱(いみな)を避けて薯薬と改め,また,宋の英宗の諱が署であったところから山薬と改めた.」と記しています.生薬としての品質や修治法について,『本草綱目』で李時珍は「薬に入れるには野生のものが勝り,食品としては栽培したものを良しとする.」と述べ,また寇宗奭の説を引用して「薬に入れるには生(なま)で乾したものを貴ぶ.故に古方にはいずれも乾山薬を用いるとある.生(なま)では性が滑であって薬に入れられず,熟して(よく熱を通して)はただ食べられるだけだからだ.」と記しています.
『本草綱目』の主治の項で,李時珍は「腎気を益し,脾,胃を健やかにし,洩利を止め,痰涎を化し,皮,毛を潤す.」と述べるとともに,朱震亭(朱丹渓)の説「生(なま)でついて腫硬毒に貼ればよく消散する.」を示し,外用することを紹介しています.日本では,貝原益軒がこの朱丹渓の説を試し,『大和本草』に「腫テ硬キ瘡ニ,生ニテスリクダキテ付レバ消散スト丹渓云ヘリ.今試ルニ有效.婦人乳腫痛不可忍,生ナル薯蕷ヲスリクダキ付ル,其效アリ.痒ヲ忍ブベシ.」と記しています.また,『本朝食鑑』には,腫痛の他に,やけどやただれに同様に外用する方法が記されています.ヤマノイモやナガイモの芋はすりおろして食べると手や口の周りが痒くなることがあります.芋をすりおろしたものを,痒くなるにもかかわらず,患部に貼る療法を考えた先人たちには,その豊かな発想力に驚くとともに,病を治そうという強い意志を感じます.