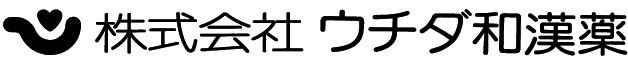基源:クコ Lycium chinense Miller 又はナガバクコ Lycium barbarum Linne(ナス科 Solanaceae)の果実(枸杞子),根皮(地骨皮)
クコ(中国名:枸杞)Lycium chinense は8〜9月頃に淡紫色の花をつけるナス科の低木です。原産地は中国で,日本では北海道を除く各地の荒れ地や土手などに生え,秋には果実が鮮やかな赤色に熟します。ナガバクコ(中国名:寧夏枸杞)L. barbarum も中国原産で日本には自生しませんが,中国の西北部に分布し,寧夏地区を中心に栽培が盛んに行われています。主にこれら2種の果実を「枸杞子」,根皮を「地骨皮」,葉を「枸杞葉」として薬用にします。『日本薬局方』には,枸杞子と地骨皮が第十四改正第二追補から収載され,上記2種が原植物に規定されています。一方,『中華人民共和国薬典』では,枸杞子にはナガバクコの果実のみが定められています。クコとナガバクコでは,果実の味が異なり,クコでは甘味の他にやや苦味があり,ナガバクコでは甘味だけで苦味はないといわれています。
「枸杞」は『神農本草経』の上品に「味苦寒。五内の邪気,熱中消渇,周痺をつかさどる。久しく服すれば筋骨を堅くし,身を軽くし,老いない」と収載されています。しかし,同書には「枸杞」とあるだけで,薬用部位は特定されていません。李時珍はこのことについて,「『神農本草経』では,ただ枸杞というだけで,その根,茎,葉,子のいずれとも指定していない。『神農本草経』に記された気,主治は,根,苗,花,実を通じて言っており,初めには区別しなかったのだろう。後世に及んで枸杞子を滋補薬とし,地骨皮を退熱薬としたのだ」と考察しています。部位別の性味と主治について,李時珍は「枸杞の苗,葉は苦く甘く涼であり,上焦,心,肺の客熱のものに適する。根は甘く淡く寒であり,下焦,肝,腎の虚熱のものに適する。子は甘く平であり,熱を退けることはできず,腎を補し,肺を潤し,精を生じ,気を益する。分けて用いればそれぞれ主とするところがあり,兼ねて用いれば一挙両得する」と述べています。
分けて使用する場合には,「地骨皮」は「滋陰至宝湯」,「清心蓮子飲」などの処方に配剤されます。また「地仙散」は,地骨皮,防風,炙甘草,生姜を煎じたもので,骨蒸煩熱,虚労煩熱,大病後の煩熱に用いられます。日本の民間療法では,いぼ痔が痛むとき,口内炎で爛れたとき,はやり目などには,地骨皮の煎じ汁で洗うとよいとされています。
「枸杞子」は「杞菊地黄丸」,「枸杞丸」などの丸剤に用いられます。修治法は,『本草綱目』に「枝や柄を除き,色つやのよいものを選び,洗浄してから酒で一晩潤し,つきつぶして薬にいれる」と記されています。なお,古くなると色が黒くなるので注意が必要です。「枸杞酒」は生の実をつき砕いて絹の袋に入れるか,砕かないで実が全部浸かる程度の量の焼酎や清酒を入れて作ります。『外台秘要』には「枸杞酒は,虚を補い,労熱を去り,肌肉を長じ,顔色を益し,人を肥健にし,肝虚して涙を下すものを治す」と記され,日本でも好んで用いられています。
「枸杞葉」は,江戸時代の日本では,主に食用として地骨皮や枸杞子よりもよく用いられていたようです。『本朝食鑑』には「最も柔軟な枸杞の若芽・新葉は,蔬菜として食べる。また蒸し焙って,お茶の代りに飲むのもよい。あるいは,陰乾して貯蔵し,使用時に水中に浸して煮て食するのもよいものである。近ごろ世俗では一般に,滋養・壮陽のものとしてこれを嗜むといわれている」「枸杞の葉飯も人を益する。時々食するとよい」などと記され,また,『日用食性』にもクコの葉を煮て食べたり,お茶の代わりに飲むとよいと記されています。枸杞飯は,若葉をさっとゆがいて,薄い塩味をつけ,炊き上がったごはんに混ぜ込んで作ります。
クコは比較的栽培が簡単で,挿し木で簡単に増やすことができる植物です。クコを自分で育て,春には新鮮な若葉で枸杞飯を作り,秋には果実で枸杞酒を漬け,日々の生活に取り入れたいものです。ただし,胃腸が虚弱で,消化不良,下痢気味の人には適さないので,控えたほうがよいそうです。