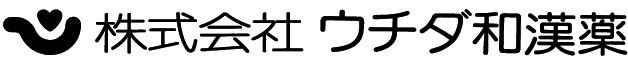基源:キク科(Compositae)のベニバナ Carthamus tinctorius L. の管状花をそのまま又は黄色色素の大部分を除いたもので,ときに圧搾して板状としたもの
奈良の東大寺二月堂では,毎年3月にお水取り(修二会)の行事が行われます。その際に二月堂の十一面観音に捧げられる椿の造り花の花弁には,紅(ベニ)で染めた深紅の和紙が使われます。深紅,白,クチナシで染めた黄色の3色の和紙を組み合わせた造り花を,椿の生木につけて飾ります。この和紙を染める紅は,ベニバナの紅色色素を分離したものです。ベニバナには,水に不溶の紅色色素 carthamin と水溶性の黄色色素 safflor yellowが含まれています。紅を得る行程は複雑です。まず,花(管状花)を水の中で揉み,水溶性の黄色色素を除きます。その後,藁灰汁を加えて紅色色素を溶出させます。紅色色素はアルカリ性で溶出する性質があります。そこに米酢を加えて中性にし,麻布などの植物繊維に紅色色素を吸着させます。再び,藁灰汁を加えて紅色色素を溶出させ,色素の濃度を高めます。次に烏梅の水溶液を加えて酸性にすると,紅色色素が析出して沈殿し,それを集めたものが紅です。紅は,日本で古くから染料以外にも化粧用など,生活にかかせないものでした。かつては高貴な身分の人にしか許されないものでしたが,江戸時代には庶民の間にもひろがり,ベニバナの栽培,紅の製造が盛んに行われました。現代では,口紅や染料は化学合成品に替わり,紅の需要は少なくなってしまいましたが,先の東大寺のお水取りのような伝統行事などの中に生き続けています。
生薬の「紅花」は『開宝本草』に「紅藍花」として初めて収載されました。「紅花」を含む最も古い漢方処方は,『金匱要略』婦人雑病篇の「紅藍花酒方」です。この処方は紅花を酒で煎じたもので,「婦人六十二種の風,及び腹中血気刺痛をつかさどる」とあります。このように紅花は,婦人薬として重要な生薬で,月経不順,冷え症,更年期障害,血行障害の治療に用いられます。日本では,女性たちはベニバナから製した紅を唇につけたり,紅染めの襦袢を身につけたりしました。それは,美しくみせるという効果の他に,薬としての効能により血行がよくなって体が温まるなど女性の健康を保つ作用があったとも考えられます。実際に,染色に携わる人の話では,紅で染めていると手が温かくなってくるといいます。
ベニバナは,古くから栽培化された植物で,これまでに野生品は見つかっておらず,原産地は特定されていません。De Candolle が著した『栽培植物の起源』には「最も古くから栽培されている植物の一つである。花は黄または赤に染色するために利用され,種子は油を生じる。古代エジプト人のミイラを包んでいた布はベニバナで染められている。また,インドでは,ベニバナに対して,2つのサンスクリット名(Cusumbha 及び Kamalottara)があることから,古くから栽培されていたに違いない」と記されています。このように,ベニバナは,エジプト,インドでは,古くから使用されており,これらの地域の周辺あるいは中間点が原産地ではないかとする意見があります。ベニバナは,やがて東アジアにも伝えられ,紀元前の中国では,匈奴の人々が焉支山周辺で栽培を行っていました。前漢の頃,匈奴は戦いに負け,焉支山を奪われてしまいました。匈奴の女性たちは,ベニバナで製した臙脂(紅)で化粧をしていたことから,匈奴の王は「失我焉支山使我婦女無顔色(焉支山を失って,女性達に紅で化粧をさせてあげることができなくなってしまった)」と嘆いたとされています。その後,仏教文化とともに中国から朝鮮半島を経て,日本に伝えられたと考えられています。ベニバナは,『延喜式』によると,全国24の国々に賦課されており,九州,四国,東北地方以外の各地で栽培されていました。江戸時代以降,現在の山形県の最上川流域の平野が,土が肥えて水はけがよいことから,一大産地になりました。
ベニバナは,プランターなど少ないスペースで栽培することもできます。自分で育てて,生長する様子を観察したり,花を摘んで布を染めてみたり,また,ドライフラワーにしてみるのはいかがでしょうか。生薬の原植物に接することで,生薬に対する興味がより広がることと思います。