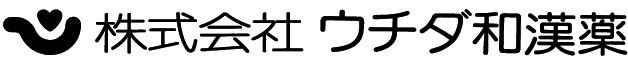基源:ウグイスガイ科(Pteriidae)のアコヤガイ Pinctada martensii Dunker(海水産)あるいはイシガイ科(Unionidae)のヒレイケチョウガイ Hyriopsis cumingii Lea(淡水産)などの外套膜組織中に形成された顆粒状物質(真珠)
珍珠は真珠に由来する生薬です。真珠は薬物としてよりも宝石として馴染み深いものです。他の宝石とは異なり、動物が生み出すもので、また磨かなくても美しい光沢を放つという一種独特な宝石です。真珠というと、日本ではアコヤガイの養殖真珠が一般的で、宝飾品として使われている球状のものが思い浮かびます。しかし、珍珠の生薬標本を見ると、小さな不定形のものが多く、真珠には様々な色や形のものがあることがわかります。
珍珠は、『開宝本草』に「真珠」の名で収載された生薬で、「寒、無毒。手足の皮膚の逆臚をつかさどる。心を鎮める。綿につつんで耳を塞げば聾をつかさどる。顔につければ人を潤沢にし、顔色をよくする。粉を目に点ずれば膚瞖、障膜をつかさどる」と記されています。現代では、驚悸失眠、驚風癲癇、目赤翳障、瘡瘍不斂、皮膚色斑などに応用されます。
真珠を生み出す貝は、海水産ではアコヤガイ、クロチョウガイ Pinctada margaritifera L.、シロチョウガイ Pinctada maxima Jameson、アワビ類などがあり、淡水産ではヒレイケチョウガイ、イケチョウガイ Hyriopsis schlegeli Martens、カワシンジュガイ Margaritifera margaritifera L.、カラスガイ Cristaria plicata Leach、ドブガイ Anodonta woodiana Lea などが挙げられます。これらの貝に共通する特徴は、貝殻の内側に真珠層という美しい色と光沢を有することです。この真珠層は、真珠を構成する層と同じ構造で、炭酸カルシウムの結晶とコンキリオンというたんぱく質からなります。真珠の光沢は、光がこの炭酸カルシウムの板状結晶とコンキリオンの薄層からなる層状構造を通る際に緩衝作用を起こすことによっています。真珠層の形成には貝の外套膜が関わっています。外套膜とは、貝の中身を包みこむように貝殻と接する膜で、膜の上皮細胞からは真珠層を構成する物質が分泌されます。現在の真珠には天然真珠と養殖真珠があり、天然真珠は貝に自然に生じた真珠で、球形は少なく、不整形が多くみられます。大きさは直径数㎝になることもありますが、多くは「ケシ」とよばれる直径数㎜の小さなものです。天然真珠がどのように形成されるかについては不明確な点が多いですが、真珠が形成された場所に外套膜の上皮細胞が袋状に変化した真珠袋という組織があることが明らかにされています。この真珠袋にヒントを得て真珠の養殖方法が考案されました。海水産ではアコヤガイ、淡水産ではヒレイケチョウガイによる養殖が広く行われています。
天然真珠、養殖真珠ともに、宝飾品として形・色・光などが劣るものが生薬として使用されています。また核を用いて養殖した真珠は表面の真珠層のみを薬用とします。『海薬本草』に「粉のようにして用いる。細かくないと人の臓腑を傷める」と記されているように、用いる際には、細かい粉末にします。『本草綱目』には「絹袋に盛り、豆腐の中へ入れてしばらく煮る。このようにすれば珠を傷めない」と粉末の作り方について記されています。現在では、真珠を粉にしてから水飛法で精製粉末にし、丸剤や散剤として内服するか、外用しています。
日本で真珠の養殖が本格的に開始されたのは明治時代以降で、江戸時代は天然の真珠が薬用にされていました。『和漢三才図会』によるとアワビの真珠が最も良いとされていましたが、得難いものでした。次に良いものは「伊勢真珠」と称するアコヤガイの真珠で、装飾用に用いない小さいものを薬用にしました。また「尾張真珠」と称するアサリなどの貝から取れた珠も薬用にされましたが、品質は劣るものでした。これらの真珠を気付け薬や眼薬に配合して用いていました。
日本では、かつては琵琶湖で固有種のイケチョウガイを用いた真珠養殖も盛んに行われていました。琵琶湖産の真珠は「ビワパール」として世界的にも人気がありましたが、その後水質の悪化など環境の変化により養殖は衰退し、現在ではイケチョウガイの絶滅が危惧されるに至っています。真珠は貝がつくりだす宝石であり、また重要な薬用資源です。このイケチョウガイの例は、真珠をはじめとする生物資源を永続的に利用するためには、自然環境を守り続けるように努めることが大切であることを教えてくれます。