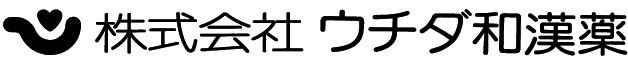基源:ヤシ科(Palmae)のビンロウAreca catechu L. の成熟果実の種子(檳榔子)・成熟果実の果皮(大腹皮)
ヤシの仲間のビンロウはマレー半島原産で、オセアニアからアフリカ東岸に至る広い地域に分布し、高さ20〜30mにも達する常緑高木です。ビンロウの成熟した果実の種子、果皮を乾燥したものが、それぞれ生薬の檳榔子、大腹皮です。檳榔子の断面には大理石調の美しい網目模様が認められますが、これは種皮が胚乳に入り込んでできたものと考えられています。日本では、ごく一部地域を除き,露地栽培は困難な植物です。
東南アジアでは、ビンロウの果実とコショウ科のキンマ Piper betle L. の葉が石灰と共に道ばたで売られており、それらを一緒に嗜好品としてガムのようにかむ習慣(ベテル・チューイング)があります。咀嚼により、唾液の分泌が促され、また唾液が赤く染まり、それを路上に吐き出す光景が、東南アジアへの日本人旅行者に海外を強く実感させたことでしょう。この赤色はビンロウの果実に大量に含まれるタンニン類に因むと考えられます。グアムでは少なくとも2000年前からベテル・チューイングが行われてきたと言われており、ビンロウが古くから人々の生活に密着していたことがうかがえます。一般的には、このベテル・チューイングによって軽い陶酔感が得られるとされており、また噛んでいる人には寄生虫症が少ないことが知られています。しかしながら、近年、口腔がんとの関連性が指摘されており、興味本位の使用は控えるべきでしょう。また、街中の景観を良くするために使用を禁止する地域が出始めたこともあって、ビンロウの果実の使用量は年々減少の一途をたどっているようです。
日本に目を向けると、正倉院薬物の献物帳である『種々薬帳』に記された「檳榔子七百枚」という記載や、また日本書紀中の檳榔についての記述から、檳榔子が奈良時代にはすでに日本に伝来していたことがうかがえます。当時の使用法は定かではありませんが、虫下しとしてあるいはお歯黒や染物(檳榔子染)に用いられたのではないでしょうか。当時、ビンロウは日本で栽植されていたはずはなく、舶来品が使用されていたのでしょう。
檳榔子には数種のアルカロイドが含まれることが知られています。代表的なものとして、ニコチン酸に類似した化学構造で表されるアレコリンがあり、副交感神経興奮作用ならびに中枢抑制作用があるとされます。一方で、檳榔子には単味で駆虫作用があることがわかっており、19世紀中頃には産地から遠く離れたヨーロッパで珍重されていたようです。同様の作用は先述のアレコリンにも認められ、獣医科治療において条虫の駆虫薬として使用されています。配剤される漢方処方としては、女神散、九味檳榔湯などがあります。
一方、大腹皮は檳榔子に比べて地味な印象を受けます。含有成分についての研究が十分ではなく、カロテノイドを含む程度しかわかっていません。配剤される処方も、分消湯や導水茯苓湯などなじみの薄いものばかりです。薬効に関しては、健胃作用など檳榔子と共通する点もありますが、檳榔子は駆虫作用、瀉下作用が優位であるのに対して、大腹皮は止瀉作用を示すことが特徴的です。
ビンロウは漢字では「檳榔」と表記されます。この二つの漢字のつくりは、共に大切な客を意味します。すなわち、「檳榔」は客をもてなす際に用いられた果実という意味を持ちます。実際に、ベトナムをはじめとする東南アジアの国々には今でも、賓客をもてなす際にビンロウを用いる地域があります。また、一部地域では、結婚式の際にキンマとビンロウを配る習慣があります。これは、この両者が夫婦のシンボルとされているからともいわれています。加えて、ヒンズー教においても檳榔子は吉兆と純粋の象徴とされており、檳榔子抜きで催される儀式はないとも言われます。
嗜好品からお供物と幅広く用いられるビンロウですが、ベテル・チューイングが衰退しつつある中、ビンロウが持つ本来の薬効のさらなる探索が必要なように思えてきました。