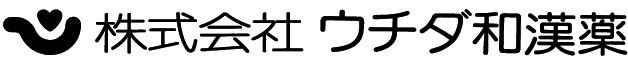基源:クワ科(Moraceae)のオオイタビFicus pumila L.あるいはキョウチクトウ科(Apocynaceae)のタイワンテイカカズラTrachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.の幼い枝を乾燥したもの.その他,ニシキギ科(Celastraceae)のツルマサキEuonymus fortune (Turcz.) Hand.-Mazz. var. radicans (Sieb. ex Miq.) Rehd.,ブドウ科(Vitaceae)のツタParthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.,アカネ科(Rubiaceae)のシラタマカズラPsychotria serpens L.などが用いられる.
能『定家』では,後白河天皇の皇女である式子内親王の亡霊と旅の僧とのやり取りが表現されています.鎌倉時代の歌人,藤原定家は内親王と恋に落ちましたが,その想いは内親王の没後もやむことなく,いつしか蔦葛になって内親王の墓に絡みつき,それは取り除いてもすぐに繁茂するようになりました.内親王の亡霊は僧に弔いを請い,僧が法華経の薬草喩品を唱えると成仏したという話です.この話の中で,内親王のお墓に絡みついていた赤く紅葉する葛が定家葛と呼ばれるようになったそうです.このテイカカズラやその仲間も生薬として用いられます.
防已や木通などの植物の蔓を用いる生薬は,その基源に関して混乱がしばしば見受けられますが,蔓や葉が用いられるラクセキトウに関しても一筋縄ではいかないようです.ラクセキトウは『神農本草経』の上品に落石(絡石)の名で収載されています.『唐本注』には「冬夏常に青く,実は黒くて丸い」とあり,これは,常緑であり紅葉せず,加えて果嚢が熟すと紫色になるオオイタビに良く似ています.加えて,「石の間にあるものは葉が細く厚く丸くて短いが,木に絡まるものは葉が大きくて薄い」とあり,幼い葉は小さいが成長し立ち上がった枝には大きな葉をつけるオオイタビの特徴に良く合致します.『植物名実図考』には,気根を伸ばして這う姿や互生で丸く短い葉が描かれており,オオイタビに良く似ています.この他にも種々の本草書においてオオイタビと思われる記載が認められるため,オオイタビを正品とする説が有力なようです.一方で,『蜀本草』では花は白く種子は黒いと書かれているなど,歴代の本草書の中にはタイワンテイカカズラによく合致するものも少なからず認められます.おそらく両種は混用されてきたのでしょう.現在の『中国薬典』では,「絡石藤は絡石(タイワンテイカカズラ)の葉やつる性の茎」と規定されています.一方で,乳児縄T. cathayanum Schneid.,薜茘藤(オオイタビ),地瓜藤F. tikoua Bur.,穿根藤(シラタマカズラ),扶芳藤(ツルマサキ),華中五味子Schisandra sphenanthera Wils. et Rehd.などの混入・流通が指摘されています.
オオイタビは多数の5環性トリテルペノイドのほかクマリン類,そして,ルチンなどのフラボノイドが多く含まれていると報告されています.一方,タイワンテイカカズラの葉にはフラボノイドであるアピゲニン,ルテオリンやその配糖体が多く含有されています.つる性の茎からはトラケロゲニンやアルクチゲニンなどのリグナン類が多数報告されています.このアルクチゲニンは,通常の抗がん剤が効きにくい膵臓がんの細胞に対して栄養飢餓状態において毒性を示すことが判明し,近年注目されています.また,数種のインドールアルカロイドの含有が報告されていますが,同じキョウチクトウ科の植物ニチニチソウに含まれる猛毒のビンカアルカロイドの報告は見当たりません.切断面から出る乳液は皮膚につくとかぶれるようですが,毒性自体はニチニチソウほど強くないようです.
ラクセキトウの性味について,『神農本草経』では苦・温とされていますが,同時に熱性の症状を治すという旨の記載もあり,なんだかはっきりしません.『名医別録』では微寒,『本草綱目』では甘く微酸で苦くないと記載されています.このように性味が一致しませんが,これらは基源の混乱によるものでしょう.『中国薬典』の絡石の項には性味が苦,微寒,帰経は心・肺・腎と記載されています.祛風・通絡・涼血・退熱の効があり,桔梗・射干などと共に絡石湯として咽頭が痛み閉塞するものに用いられます.