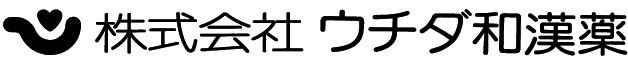基源:ハマウツボ科(Orobanchaceae)の ホンオニクCistanche salsa (C. A. Mey.) Beck, C. deserticola Y. S. Ma, カンカニクジュヨウC. tubulosa (Schenk.) R. Wight のりん片を付けた肉質茎
ハマウツボ科という寄生植物で構成される分類群があります。日本に分布する種類ではカワラヨモギに寄生するハマウツボやススキなどに寄生するナンバンギセルなどがあります。この科に属する植物は寄生元から養分を得るため、植物体には葉緑素がなく黄色や白色を帯びています。葉は退化して小さな鱗片状になっています。花は両性花で先が5裂する筒状の唇形花、その後、さく果が結実し細かい種子ができます。
肉蓯蓉はハマウツボ科 Cistanche 属植物に由来する生薬です。原植物は日本には分布がなく、中央アジアからシベリア、モンゴル、中国北西部の砂漠地帯に分布しています。アカザ科の植物などに寄生します。この属は多肉質で肥厚した茎を有し、高さ1メートルに達するものもあります。多数の花がこの円柱形の茎に穂状花序を作って密生します。この奇妙な植物形態は古来の本草家を悩ませてきました。
『神農本草経集注』には「これは馬の多い處にあるもので、野馬の精液が地に落ちてそれから生ずるものだという」と記載される一方、『日華子諸家本草』には「勃落樹の下や土塹の上に生ずるもので、馬の交尾し得る處ではない。陶氏(神農本草経集注)の説は誤っている」と反論も見られます。『図経本草』では「舊説に、野馬の遺した精滴から生ずるものだというが、現に西方の者の話では、大木の間、および土塹や垣の中に多く生ずるというのだから、これはやはりそうした別の一種類の植物があるものと見える。或はそのものの発生の初期は馬の精瀝から生じ、その後植物として繁殖したものか、」との記載があり、植物という認識に落ち着いたようです。
肉蓯蓉の真の正体はともかく、入手困難な高価な生薬であり、それゆえ偽品も存在したようです。『本草綱目』では「震享曰く」に続けて「蓋し蓯蓉は手にいれることの甚だ稀なもので、世間では多く金蓮根を塩盆の中で加工して擬物を作り、又、草蓯蓉をこのものと擬称する場合が多いから、使用するには余程慎重な吟味を要する」、また「嘉謨曰く」に続けて「今世間では松の若芽を塩で潤して贋物を作っている」との記載があります。
肉蓯蓉は古来、強壮・強精作用に優れた生薬でした。『神農本草経集注』には「五労、七傷を主治し、中を補い、茎中の寒熱痛を除き、五臓を養い、陰を強くし、精気を益し、子多からしむ。婦人の癥瘕を治す」とあり、『日華子本草』には「男子の絶陽で興奮せぬもの、婦人の絶陰で妊娠せぬものを治す。五臓を潤おし、肌肉を長じ、腰膝を暖める。男子の洩精、血遺瀝、婦人の帯下、陰痛を治す」とあります。『本草綱目』には肉蓯蓉という名称の由来も合わせて「この物は補の功用があって而もそれが峻烈でないところから從容なる名称がある。從容とは和らぎ緩やかなるの形容である」と記載しています。
肉蓯蓉は春または秋に採集されたものから調製されます。3月が良く、これより遅くなると中空になるそうです。春に採集したものは砂中に半分埋め、晒干しし「淡大芸、甜大芸」という名称に、秋のものは水分が多いため塩湖中に1〜3年漬けておき、これ晒干ししたものを「塩大芸、鹹大芸」という名称にされています。後者を薬用にする際には水に浸し、1日1〜2回水を換え、塩分がなくなるまで洗い去ります。日本に輸入されている肉蓯蓉は「淡大芸」の方です。太くて堅実で、鱗片葉で密に覆われ、褐色で、質は柔らかく潤いのあるものが良いとされてきました。産地は内モンゴル自治区が生産量最大で、甘粛、新疆、青海などでも生産されています。
肉蓯蓉に対して草蓯蓉という生薬があります。草蓯蓉も同じくハマウツボ科に属するオニク(別名キムラタケ)Boschniakia rossica の肉質茎に由来する生薬です。オニクは日本にも分布することから、誤って肉蓯蓉の原植物に充てたこともありましたが、和肉蓯蓉と称して代用にされています。富士山のオニクは有名で、以前は強壮・強精目的で売られているのを見ることができました。