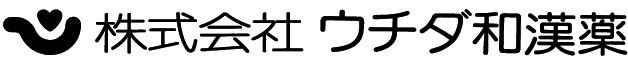基源:アカネ科(Rubiaceae)の Cephaelis ipecacuanha A. Richard 又は C. acuminata Karstenの根及び根茎
トコン(吐根)は南アメリカの先住民の間で古くから催吐剤としてやアメーバ赤痢の治療に使用されていた薬草です。種小名の「ipecacuanha」は、トゥピ族の「吐き気を催す草」を意味する現地名をポルトガル語化したものです。1570〜1600年間にポルトガルからブラジルに派遣された宣教師によって、土着民の間で疫病に使用されている薬草としてヨーロッパに紹介されました。ヨーロッパでは、元オランダ人の山師で、後にパリの医師となったアドリエン・エルベチウスがトコンを用いた処方によりルイ14世の王子らの赤痢を治療し、有効性を実証しました。それを切っ掛けにルイ14世がその処方を買い取り、赤痢の治療のほか、吐剤や去痰薬として世に広めたと伝わっています。
トコンの一原植物であるCephaelis ipecacuanha(ケパエリス イペカクアンハ)は、ブラジル奥地の高温多湿な熱帯多雨林の薄暗いジャングルの中に自生します。目立たない草本生小低木で、高さは10〜40 cm、下部の茎は木質化して横走します。葉は倒卵状楕円形で長さ5〜9 cm、茎の頂端の葉腋に10〜12個の花を頭状につけます。花は白色合弁、先端が5裂する小さなものです。果実は楕円形で長さ約1 cm、紅色から後に黒熟します。根は一部が肥厚して数珠状になり、太さ約 5 mmでところどころに細い平滑な根があります。この根だけが薬用成分を含み、数珠状の部分を乾燥させたものがトコンです。このものは Rio de Janeiro 港から輸出されることからRio ipecac (リオ吐根)と称されます。もう一種の原植物であるC. acuminataは南米コロンビア原産で、中南米で栽培されています。産地によりCartagena ipecac(カルタゲナ吐根)や Nicaragua ipecac(ニカラグア吐根)などと称されますが、Rio ipecac よりCartagena ipecacの方が根が大きくアルカロイド含量も多いようです。
薬用部位を秋から冬にかけて採集した後、天日乾燥して生薬にします。屈曲した長さ3〜15 cm、径0.3〜0.9 cmの細い円柱形で、多くはねじれ、不規則な輪節状になり、ときに分枝します。外面は灰色、暗灰褐色又は赤褐色です。根茎に由来する部位は円柱状で、対生する葉跡が認められます。弱いにおいがあり、トコン末は鼻粘膜を刺激し、苦く、辛く、不快な味がします。長さが揃い、突起物やひげ根がなく、外面が淡黄色、内面が白味を帯びているものが良品とされます。
トコンの成分研究はフランスの化学者であり薬学者である、ピエール・ジョセフ・ペルティエと、同じくフランスの生理学者、フランソワ・マジャンディーの2人によりなされました。1817年のイソキノリンアルカロイドであるエメチンの単離は植物からのアルカロイド研究の草分けとなりました。彼らはその後のストリキニーネやキニーネ、カフェインなど今なお使用され続ける医薬品の単離にも関与しています。
研究が進み、トコンのアメーバ赤痢に対する治療効果は含有するエメチンやセファエリンによるものであることが明らかになりました。抗アメーバ性のメカニズムも明らかになり、2タイプの赤痢のうち細菌性に対してはほとんど効果がないことも説明がつきました。
トコンは現在でも多くの国の薬局方に収載されています。アメーバ赤痢に使用される他、優れた催吐作用があり、適量の使用により知覚神経抹消を刺激し胃粘膜を刺激して内容物を全て吐き出させることができます。また、より少量での使用は気管粘膜の分泌を促進して去痰作用を示すことから、現在も気管支炎などの治療に使用され、生薬としても、また単一化合物エメチンとしても使用されています。それにしても、熱帯ジャングルの中の目立たない植物の根がアメーバ赤痢に有効であることを発見した陰には、ブラジルの先住民たちの薬用植物探索における地道な試行錯誤があったことが容易に想像されます。まさに、ブラジルにも神農が居たと言えそうです。