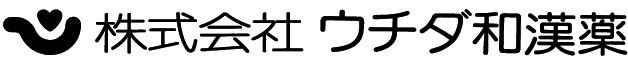基源:ゴマノハグサ科(Scrophulariaceae)の Picrorhiza kurroa Royle ex Benth. または P. scrophulariiflora Pennell の根茎を乾燥したもの.
胡黄連は現在日本では馴染みの薄い生薬ですが、古くに伝来し、正倉院薬物漢薬調査報告書によると他の薬物に混ざって胡黄連が発見されており、その後代用品が開発使用されてきたことを考えると、当時は重要薬物の一種であったことが伺えます。
中国では『開宝本草』に初収載されており、胡(イランなど西域)の黄連という字義から、シルクロードを介してもたらされた薬物の一種と考えられます。同書では『唐本』なるものを引用し、波斯国(ペルシア、現在のイラン)の海辺や陸地に産するとありますが、実際の産地とは異なることから、当時の中国にとっては未知なる国からもたらされる神秘的な薬物であったようです。
胡黄連は薬効的に黄連と同じく清熱燥湿の効能をもちますが、苦寒の性質が黄連より弱く、下焦湿熱を清導する効能にすぐれているとされています。先述の唐本には「骨蒸、労熱を主治し、肝胆を補い、目を明らかにし、冷熱、洩痢を治し、顔色を益し、腸胃を厚くし、婦人の胎蒸、虚驚を治す」とあり、形態については「苗は夏枯草の如く、根頭は烏嘴に似て、之を折ると肉が鸜鵒の眼に似たものが良い」と記載されています。一名「割孤露澤」とあり、これはゴマノハグサ科(APG分類体系ではオオバコ科)の Picrorhiza kurroaのサンスクリット名Katuka、Katurohiniなどが音訳されたものと考えられ、原産地を暗示しているようです。現にヒマラヤ地方ではこの植物の地下部を万能薬として頻用しており、アーユルヴェーダではKatukiと称して現代では黄疸、消化不良、急性ウイルス性肝炎、気管支喘息などに応用されています。
日本に伝来した胡黄連の量はもとより十分ではなかったと考えられますが、その有効性から代用品の開発に迫られたようで、鎌倉期以降代用品として「当薬」即ちセンブリが用いられるようになりました。江戸時代の『本草辧疑』の当薬の項には「葉紫花白き小草なり、山野に多し、其の味苦し、諸虫を治し腹痛を止める。古より胡黄連の代に用之。甚だ誤り也。形も味も異なるものなり。但し唐書の諸方に合わするには唐の胡黄連を用い、腹痛の和方に合わするには此の当薬を用へきなり」とあり、『大和本草』には「胡黄連、黄連に似て大也、黄ならず味苦し、蘆頭も黄連に似たり、中華より来る。此草日本にあるや未詳。千振とて秋白花を開きて葉細く味甚だ苦き小草山野にあり、又とうやくと云、国俗是を好んで用之殺蟲消積これを胡黄連と云非なり、或日倭方に胡黄連とかけるは皆せんぶりを用いるべしと云」と記載され、胡黄連の代用として当薬が用いられていた事が窺えます。なお、中国や朝鮮半島でも独自に代用品が開発され、中国東北諸省、朝鮮半島産の胡黄連はメギ科のタツタソウJeffersonia dubiaの根で「鮮黄連」とも言われています。
P. kurroa はインドやヒマラヤ地方の高山帯に分布する多年生草本で、やや乾燥した地面に這いつくばるように生えています。根元にへら形で長さ5〜10cmでやや皮質の葉がつき、根側から地を這うように長さ5〜10cmの花茎を出し、穂状花序をつけます。花を含め、全体に目立たない植物です。薬用部の根茎は円柱形、少し木質を帯び、長さ15〜25 cm、苦味が強いものです。
胡黄連には苦味成分であるクトキンやトキオール、クトキステロールなどが含まれ、抗菌、抗真菌、利胆作用などが報告されています。また、代用品の当薬には苦味成分であるスウェルチアマリンやアマロスウェリン、アマロゲンチンなどが含まれ、胆汁、膵液、唾液などの分泌促進作用などが報告されています。
P. kurroa とセンブリでは植物学的に全く異なり、薬用部位も異なりますが、その苦味と薬効の類似性から代用品として用いられたことが推察されます。高山植物で、根茎が長さ10cm以上に育つにはそれなりの年月を要します。ヒマラヤ高山帯の希少資源植物として、保護をしながら有効利用を図る必要がある植物です。それにしても、遠くヒマラヤから中国を経由してはるばる日本へ渡り、正倉院に納められ、代用品が開発されるなど大切に扱われてきたことなど、ロマンを感じさせる薬用植物です。