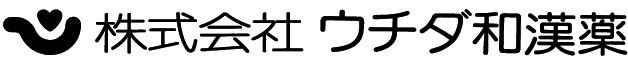基源:キンポウゲ科(Ranunculaceae)のオウレン Coptis japonica Makino, Coptis chinensis Franchet,Coptis deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao 又は Coptis teeta Wallich の根をほとんど除いた根茎。
最近,某テレビ局の人気番組で福井県の黄連生産者が紹介されました。この番組を通して「黄連」の名称や生薬の形状が日本中に放送されました。生薬関連の業務に従事している国産生薬の生産現場や生薬の価格,後継者問題など改めて理解することができたと思います。この番組制作者は意図していなかったと思いますが,国産生薬の抱える本質的な問題を提起した,まさに時宜を得たものでした。
平成28年度のデータによると日本における黄連の使用量は 41,931 kg で,そのうち国産品は 1,501 kg(3.6%)です(生薬学雑誌, 73, 16-35, 2019)。国産黄連の原植物は,第十七改正日本薬局方ではオウレン Coptis japonica Makino と規定される種ですが,実際にはオウレンはさらに3変種に分けられています。すなわちキクバオウレンCoptis japonica Makino var. anemonifolia H.Ohba,セリバオウレン Coptis japonica Makino var. major Satake,コセリバオウレンCoptis japonica Makino var. japonica です。これら3変種は葉の切れ込みの深さから分けられています。切れ込みが浅いもの,すなわち1回3出複葉のものは葉の形状がキクに似ているのでキクバオウレンとされています。2回3出複葉のモノはセリバオウレン,3回3出複葉のものはコセリバオウレンと名付けられています。キクバオウレンは日本海側を中心に,セリバオウレンは本州西日本を中心に四国まで,コセリバオウレンは太平洋側を中心に分布しています。日本薬局方ではオウレンCoptis japonica と記載されていますから,これらオウレンの3変種はいずれも適合する分類群です。しかしコセリバオウレンは,その根茎があまり発達しない特性であることから生薬として使用されることはありませんでした。一方,『延喜式(905-927)』には,加賀国と能登国,すなわち現在の石川県周辺で黄連が産していたことが記載されています。江戸時代には,例えば『物類品隲(1763)』には「加賀産菊葉のもの上品」とあるように,キクバオウレンに由来する黄連が流通していました。しかも品質が良かったらしく,昭和初期まで海外に輸出されていたことも記録が残っています。セリバオウレンに由来する黄連には越前黄連,因州黄連,丹波黄連などあり,長年使用されてきました。
日本薬局方では第九改正から,オウレンは Coptis japonica および他の同属植物という記載が追加されました。この頃から中国産黄連の日本への輸入が増加し始めました。この事実を受けて第十四改正では Coptis japonica に加え中国産の3種である Coptis chinensis,Coptis deltoidea,Coptis teeta が明記されました。日本の医療現場で使用される黄連は,価格面で優位な中国産黄連に次第に入れ替わってきました。その結果,国産は現在の比率である4%以下にまで落ち込んでしまいました。日本産黄連について,キクバオウレンに由来するものは野生品を使用していたと考えられます。栽培化に移行する際,根茎部の成長が早いセリバオウレンが選択された結果,品質が良いとされてきたキクバオウレンに由来する野生黄連も消滅しました。セリバオウレンの日本国内での生産地としては,越前黄連の福井県大野市および丹波黄連の兵庫県丹波市山南などがありました。いずれもその地域の気象環境や生活様式に合わせた林間栽培法や畑栽培法を確立していました。黄連の加工は,収穫後のひげ根と根茎を分別する操作が必要とされます。密集した根茎を分割する方法,火でひげ根を焼く方法など,繊細で高い技術を要する工程があり,しかも機械化が難しく手間がかかるものです。価格面で中国産との競争ができなくなった結果,生産を断念する方や後継者問題から生産者は減少の一途とたどっています。
現在,黄連の生産地としては越前黄連の福井県大野市が残っています。今回のテレビ放映は私達にも改めて国産生薬について考えさせる切っ掛けになりました。