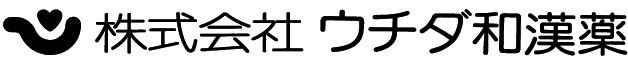基源:ツバキ科 (Theaceae) のチャノキ Camellia sinensis Kuntze の葉を乾燥したもの。
吉川英治の『三国志』は,劉備が母親のために高価な「茶」を購入する場面から物語は始まります。お茶は現在,飲料として一般的ですが,この時代は入手が困難であり希少価値とともに薬としての役割が期待されていたことはよく知られています。実際,茶葉は紀元前10世紀頃の周の時代に薬用として使用されはじめ,次第に嗜好品となったとされています。劉備の時代,茶葉は限られた地域に自生する野生株からわずかに生産される貴重品であったに違いありません。当時の飲用方法は現在のような茶葉にお湯を注ぐという方法ではなく,陳皮や生姜などと一緒に煮てスープのようにしていたようです。栽培が普及し,製茶技術が確立したのは8世紀の唐の時代とされ,宋代の『図経本草(1062年)』には「春中に始めて生えた嫩葉を蒸し焙じて苦水を去り,末にして飲むべきもので,古代に食した方法と甚だ異る」と,抹茶のような飲み方の記載もあります。
日本では『延喜式(927年)』に茶園の記録があることから,この頃には栽培化されていたようです。最澄(767-822)が留学先の唐から持ち帰ったとも言われています。日本でも茶が貴重であった時代はやはり薬用としての役割が主でした。その後,栄西(1141-1215)が苗木を持ち込み,鎌倉・室町・江戸時代を通じて茶文化が一般に普及すると同時に,宇治や静岡を中心に産地が形成され,茶は次第に嗜好品という性質が強くなりました。
茶葉の薬効について,唐代の『本草拾遺(739年)』には「苦し,寒なり。久しく食すれば人をして痩せしめ,人の脂を去り,睡らざらしめる」,明代の『本草綱目(1596年)』には「酒食の毒を解し,人をして神思,闇に爽やかにして昏せず睡らざらしめる」とあり,茶のカフェインによる覚醒作用も記載されています。味の「苦味,渋み」はタンニンやアルカロイドであるカフェイン,テオフィリンによるものです。またアミノ酸のテアニンはうま味に関与しています。カフェインには中枢神経系の興奮のほか,強心,利尿,血管拡張などの作用もあります。テオフィリンの強心および利尿作用はカフェインよりも強いですが,中枢神経興奮作用は弱く,気管支拡張作用があります。この他,タンニンによる抗菌,収斂,止瀉作用が知られています。最近はカテキン,エピカテキンなどポリフェノールによる齲蝕(虫歯)予防,口臭抑制などが注目されるようになりました。
茶葉を産するチャノキは常緑の樹木で,ツバキに似た径3センチメートル程の白い5弁の花を咲かせます。種類は大きく2つ,高木(10メートル)で大型の葉をつける変種アッサミカ Camellia sinensis var. assamica と,低木(2, 3 メートル)で小型の葉をつける変種シネンシスC. sinensis var. sinensisに分けられます。アッサミカは耐寒性が弱く,タンニンを多く含み酸化酵素の働きが強く主に紅茶に加工され,シネンシスは耐寒性が強く,タンニン含量が少なく酸化酵素の働きも弱いため主に緑茶用にされます。酸化酵素の働きにより発酵反応が起こります。緑茶に加工されるものはシネンシス系であり,発酵を止めて緑色を保たせています。日本に普及しているチャノキはシネンシス系の中でも小型のタイプですが,アッサミカの遺伝子をも含んでおり,遺伝的な背景が複雑になっているようです。
カフェインを含有する植物は,チャノキ以外にコーヒーノキやカカオなど種類が少なく希少な種です。このチャノキを見つけ出したのは中国南部から東南アジアにかけて生活していた少数民族と考えられています。このチャノキが発酵技術により烏龍茶や紅茶に加工され,また緑茶として世界中に普及していることは奇跡的なことです。特に中国のお茶の販売店には数多くの種類や等級別のお茶が並んでおり,価格も様々で,お茶の長年の利用の歴史を物語っています。貴少という点では香港返還式典の際に使用された大紅袍が有名でしょうか。年間生産量が1kgに満たない茶葉で,薬効と名称にまつわる伝説が残っています。