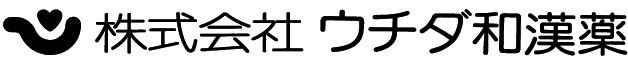基源:バラ科(Rosaceae) ビワ Eriobotrya japonica(Thunb.)Lindl. の葉。
今年も残暑厳しい 9月を迎えていることと存じます。梅雨がない北海道を除き、8月 2日を最後に全ての地域で梅雨明けが発表されました。気象庁の発表によると 8月に入ってからの梅雨明けは 4年ぶりで,また, 7月の月平均気温が統計を開始した 126年間で最も高温だったとのことです。9月とはいえ引き続き暑さ対策が必要な日々が続きそうです。
江戸の夏も現代に引けを取らず暑い日があったようです。シーボルトが再来日した時に記した『シーボルト日記(独文日記)』の中に「(1861年8月14日) 7月と 8月,江戸湾と江戸および周辺では高温。ときには木陰でも華氏 94度(摂氏 34.4℃)まで達することがある。たえず南と南東から風が吹く。これは厚くて黒い瓦をもち,その熱に包まれたこの巨大なる町が,異常なほど暖められた当然の結果である。」と記しています。(『シーボルト日記 再来日時の幕末見聞録』,石山禎一・牧幸一訳,八坂書房,p.204,2005.)このような暑い夏には枇杷葉湯売りが繁盛したことと想像します。
枇杷葉湯は中国明代の処方を参考に江戸時代に考案された日本独自の処方です。『和漢三才圖絵(1713)』に「倭方に枇杷葉湯有り。食傷(消化器を傷う)及び霍乱(嘔吐下痢の甚だしい状態)によく効く。枇杷葉,肉桂,藿香,莪朮,茣茱萸,木香,甘草を各等分あるいは異なることも有り」と記されています。また江戸時代の『丸散手引草(1800)』には「枇杷葉湯...夏月暑中リ或ハ冷物ヲ食シ菓(クダモノ)等ノ中脘ニ停滞スルノ證ニ用ユ」とあり,枇杷葉湯は「暑気あたり」にも使用されていたことがわかります。枇杷葉湯の構成生薬の組み合わせは数種類あり,茣茱萸の代わりに青皮,甘茶を使う場合もあります。同じく江戸時代の『中陵漫録(1826)』によれば,「枇杷葉湯の一薬,諸国共に通じて,毎年六月朔日より八月十五日まで貨る」と記されています(『日本随筆大成』第 3 期第 3 巻,日本随筆大成編集部,吉川弘文館,1995,p.215)。この期間は現在の 7月 1日から 9月 15日頃に相当し,まさに熱中症に注意が必要な期間です。
一方,中国では 3世紀頃には成立していたとされる『名医別録』に枇杷葉が初収載され,「味苦平,無毒。突然の乾嘔(嘔吐するときに声があっても物がでない状況)が止まらないときに気を下す」と記されています。同じくこの頃に成立していた『神農本草経集注』で陶弘景は「煮るだけの時間がない時は,ただ噛んで汁を飲んでも癒える」と記しています。しかし唐代の『新修本草』に「葉を用いる時は火で炙って,布で毛を拭きとるべき。そのようにしないと,(毛が)肺を射し咳が止まらない」とあります。葉の裏面にある綿毛は刺激があり除去することを勧めています。陶弘景が「葉をそのまま噛む」ことを勧めるとはよほど切羽詰まった状態だったのでしょうか。現在でも未処理の枇杷葉を煎剤に入れると煎液が綿毛で濁り,喉にも刺激があるので使用上の注意としては綿毛を除去して包煎するとあります。枇杷葉が配合される処方は「辛夷清肺湯」,「甘露飲」,「枇杷清肺飲」,「白芨枇杷丸」,「治百日咳方」,「枇杷葉飲」などがあります。
枇杷葉にはポリフェノールのクロロゲン酸が含まれています。処方以外の利用としては,入浴剤やビワ茶の原料,また,ビワの葉のポリフェノール酸化酵素活性に着目し,枇杷葉と茶葉を混合揉捻した発酵茶などがあります。注意が必要なものは,ビワの種子を使用した製品です。ビワの種子には高濃度のシアン化合物(アミグダリンやプルナシン)が含まれており,多量に摂取すると,健康を害する場合があります。過去に,ビワの種子を粉末にした製品からシアン化合物が高い濃度で検出され,製品が回収される事案が複数ありました。農林水産省ではビワの種子を原料とする製品の製造者や関係者に対し, 自主検査を行い,安全な食品を提供するように指導しています。
枇杷葉は昭和初期において国内生産が年間 2,000~3,700 kg でした(『薬用植物栽培法』,刈米達夫,養賢堂,昭和 18 年,p.7)が,2019年度は 3,000 kgであり(生薬学雑誌,77,24-42,2023)ほとんど変化がありません。一方,近年の年間総使用量(2008年以降)は 7,000~12,000 kg であり(生薬学雑誌,同上),枇杷葉は約 25%以上を国内産で賄うことが可能な生薬であるといえます。
さて,我が家では子どもが自分の食べたビワの実の種子を播きました。播種から 16年目の晩秋(11月)に初めて花が咲きました。しかしこの花は残念ながら結実に至りませんでした。ようやく実を食べることができたのは,播種から 18年後。桃栗三年柿八年,ビワは十八年でした。